- はじめに:痛みが消えても、それは「治った」とは限らない
- 1. 痛みとは何か? 体の“異常報告システム”
- 2. 痛みが消えた瞬間こそ注意すべき理由
- 3. 組織修復の科学:体はどうやって治るのか?
- 4. 筋膜リリースは「動かさずに流す」究極の手段
- 5. 誤解と神話の整理
- 6.科学的な裏付け
はじめに:痛みが消えても、それは「治った」とは限らない
人は痛みが和らぐと、つい「もう大丈夫」と思って動き出したくなります。
でも、それが再発や慢性化のスタートラインになることも少なくありません。
痛みのメカニズムは近年、末梢(体の末端)から中枢(脳)まで、かなり解明が進んでいます。
ペインクリニックでは「痛みの信号の発生」と「脳での知覚」の関係が詳しく研究され、
“痛みを感じる=脳の処理結果”であることもわかってきました。
つまり、痛みが消えた=脳が一時的に痛みの信号をブロックしているだけの可能性もある。
組織の修復はまだ途中。
本当に“治った”かどうかは、血流・酸素供給・細胞の再生状態を見なければ判断できません。
1. 痛みとは何か? 体の“異常報告システム”
痛み(pain)は、体に起きた異常を知らせる生体防御の警告信号です。
たとえば熱いものに触れて「痛い!」と感じるのは、体を守るための反射。
でも、その痛みが続くと、神経回路が“過敏化”してしまうことがあります。
| 種類 | 原因 | 特徴 |
|---|---|---|
| 急性痛 | 外傷・炎症・手術など | 組織損傷のサイン、短期間で治まる |
| 慢性痛 | 神経過敏・心理的要因 | 数週間〜数か月持続、ストレスとも関連 |
| 中枢性痛 | 脳・脊髄で痛み信号が暴走 | “実際には治っているのに痛い”と感じる |
つまり「痛みがない=治った」ではなく、痛みの“回路”が一時的に沈黙しただけという場合もあるのです。
2. 痛みが消えた瞬間こそ注意すべき理由
痛みが緩和すると、筋肉や関節を動かしたくなる。
しかし、これは“脳が出す一時停止信号”を無視する行為に近い。
損傷部位では、まだ修復プロセス(炎症期→増殖期→再構築期)が進行中。
この過程で無理に動かすと、再損傷や**瘢痕組織(かさぶた状の硬い結合組織)**が形成され、
可動域制限や慢性痛の原因になります。
リハビリ学で言う「痛みが取れた=免荷期の終わり」ではない
“免荷(めんか)”とは、患部に体重や負荷をかけないこと。
本来は「循環を保ちながら安静にする」のが理想です。
3. 組織修復の科学:体はどうやって治るのか?
- 炎症期(1〜5日)
免疫細胞(マクロファージ)が老廃物を除去。血流が一時的に増える。 - 増殖期(5〜14日)
線維芽細胞がコラーゲンを産生し、損傷部を“仮修復”。 - 再構築期(2週間〜数か月)
コラーゲンが再配列し、組織が元の強度を取り戻す。
→ この3段階を循環と酸素供給が支えている。
血流が悪いと、炎症が長引き、修復が遅れ、瘢痕が硬化します。
4. 筋膜リリースは「動かさずに流す」究極の手段
安静と循環。この両立を可能にするのが筋膜リリースです。
筋膜は全身の組織を包む“潤滑膜”。
ここが硬くなると、栄養や酸素を届ける間質液の流れが滞ります。
軽い吸引刺激(メディセルなど)を加えると、
皮膚と筋膜の間に微小なすき間が生まれ、血流・リンパ流が活性化。
これにより、
- 酸素・栄養の供給↑
- 炎症老廃物の排出↑
- 神経過敏の鎮静↓
といった“修復環境”が整います。
つまり「痛みをとる」ではなく、“治る体”を取り戻すステージに入るのです。
5. 誤解と神話の整理
❌ 神話①:「痛みが取れた=治った」
→ 誤り。 痛みは神経信号であり、修復とは別プロセス。
骨や筋膜はまだダメージを抱えていることも多く、再発リスクが高い。
❌ 神話②:「動かさないと固まる」
→ 半分誤り。
急性期は**“動かさずに流す”**ことが重要。
安静+軽い血流刺激(皮膚リリース)が、最も安全で効果的。
❌ 神話③:「湿布や痛み止めで十分」
→ 一時的効果のみ。
薬は痛覚をブロックするだけで、血流や細胞修復には寄与しません。
💡 神話④:「痛みの原因は筋肉だけ」
→ 誤り。 筋膜・神経・血管・メンタルが複合的に絡む。
ストレスや不安も脳の痛覚中枢を刺激し、**“脳が痛みを作る”**こともある。
🐾 神話⑤:「動物は痛みに強いから平気」
→ 大間違い。
犬や猫は痛みを隠す性質があり、見えない慢性痛を抱えがち。
メディセルなどの穏やかなタッチ刺激で血流を保ち、回復を促すことが
彼らにとっても安全なケアです。
6.科学的な裏付け
1. 脳の「痛みセンサー」が過敏になることがある
強い痛みが長引くと、脳や脊髄の“痛みセンサー”が敏感になってしまうことがわかっています。
その結果、ちょっと触れただけでも痛く感じたり、実際のケガ以上に強い痛みを感じることも。
だから「痛みを緩和すること=ただの我慢ではなく、回復のための第一歩」なんです。
2. 筋膜は“痛みの受信アンテナ”
筋膜は神経がたくさん通っている組織。硬くなったり癒着すると、それだけで痛みの原因になり得ます。
最近の研究では「腰痛の大きな原因が筋膜にあるケースもある」と報告されていて、注目を集めています。
3. 安静にしすぎると逆効果
「痛いから動かさないでおこう」と思いがちですが、実は安静にしすぎると組織が硬くなったり、動かしにくくなることが研究で確認されています。
つまり、“完全に止める”のではなく、“負荷を減らしつつ循環を良くする”ことが回復のカギになります。
4. 皮膚を吸い上げる刺激で血流アップ
カッピング(吸い玉)の研究では、皮膚をやさしく吸い上げると血流が一時的に増えることが実測されています。
メディセルのような機器も同じしくみで、循環が整うことで栄養や酸素が届きやすくなる=回復のサポートになるんです。
5. 触れること自体が「痛みのブレーキ」になる
やさしいタッチや皮膚への刺激は、脳の“痛みゲート”を一時的に閉じるといわれています。
その隙に少しずつ動かすと、回復がスムーズに進みやすいんです。
6. 心地よさ=自律神経のバランス調整
「気持ちいい」と感じる刺激は、自律神経を整える働きもあります。
特に副交感神経が優位になると、血流が良くなり、体の緊張がほぐれて痛みのつらさも和らぐ。
“癒しのタッチ”が医学的にも意味を持つ、というのは女性にとって嬉しいニュースですよね。
ペインクリニックの臨床データでは、循環改善を行ったケースは回復が平均20〜30%早いとされます。
筋膜リリースやメディセルのような機器を用いた皮膚吸引は「軟部組織の柔軟性維持」と「血流促進」に有効です。
7. 科学的根拠:筋膜リリースと修復メカニズム
🧬 ① 血流と修復速度の関係
血流が良い組織では、損傷治癒が約1.5倍早い(臨床整形データより)。
陰圧リリースで毛細血管血流が上昇し、線維芽細胞が活性化。
💉 ② コラーゲン再配列への影響
メカニカルストレス(軽い刺激)は、線維芽細胞の伸長方向を整え、
瘢痕を“しなやかに修復”させる。
🌡 ③ 神経リセット効果
リリース刺激はAβ神経線維(触覚)を介して痛覚を抑制。
これはゲートコントロール理論として知られています。
🧠 ④ 皮膚刺激と脳活動
タッチ刺激で島皮質・扁桃体の活動が低下(ストレス抑制)。
痛みと情動の結びつきを緩め、回復を促進。
8. 再発を防ぐ3つのアプローチ
- 安静+循環
痛みが消えても最低48時間は無理をしない。
軽いリリースで循環を維持。 - 再教育(リハビリ)
痛みで崩れた動作パターンを整える。
筋膜の滑走性を回復してから再トレーニングへ。 - メンタルケア
痛みは脳でも再現される。呼吸・睡眠・触覚刺激で“脳の緊張”を緩める。
9. まとめ ― 「痛みが消える」より、「治る」を目指そう
痛みがなくなることはゴールではありません。
それは、ようやく修復のスタートラインに立っただけ。
“動けるようになった”その瞬間にこそ、体を大切に扱う必要があります。
循環を保ち、皮膚と筋膜をやわらかくしておくこと。
それが、再発を防ぎ、真の回復へと導く一番の近道です。
犬や猫も同じ。
「もう元気そうだから」と安心せず、
その後の血流ケア・タッチケアを丁寧に続けてあげることが、
本当の“いたわり”なのです。
おわりに
痛みが起きるメカニズムが、かなり解明されてきました。
ペインクリニックの分野などで、痛みが起きる末梢と中枢の仕組みが説明されています。
特に、中枢のメカニズムの機能が中心。
さて、そのメカニズムにもとづいて、痛みを緩和する方法が、日の目を見るようになってきています。

痛みは、体のどこかに異常が発生しているサインだといわれています。
ただし、痛みが発生している箇所に異常が起きている場合もあれば、痛みを感じる箇所に異常が発生しているのではなく、他の場所や場合によってはメンタル的な問題から、身体の痛みとして感じることもあります。
痛みが緩和したら、それらの異常が治癒したと思いがちですが、そうとばかりは言えませんね。
特に、外傷の場合は特に注意が必要。
あきらかに、骨や筋肉などに損傷がある場合は、痛みが無くなったとしても、損傷が修復されたわけではないので。
即、動いたりすると、損傷部位に負荷がかかるので、損傷部位に悪影響が出るケースも。
組織の損傷がある場合は、当然ですがその組織が修復するまでに時間経過を必要とします。

痛みを緩和しておいて、組織の修復を促進するためには、まずは安静。専門的には免荷といいますが、体重の負荷、筋肉を動かす(収縮する)ことによってかかる負荷を、できるだけ減らす。
損傷した箇所に圧迫や腫れなどがあっても、循環が阻害されますので、修復が遅れます。
修復するためには、栄養素が供給されることが必要です。
安静な状態で、なおかつ循環が良い状態にするには、筋膜のリリースと皮膚に刺激を発生させるのが、大変有効です。
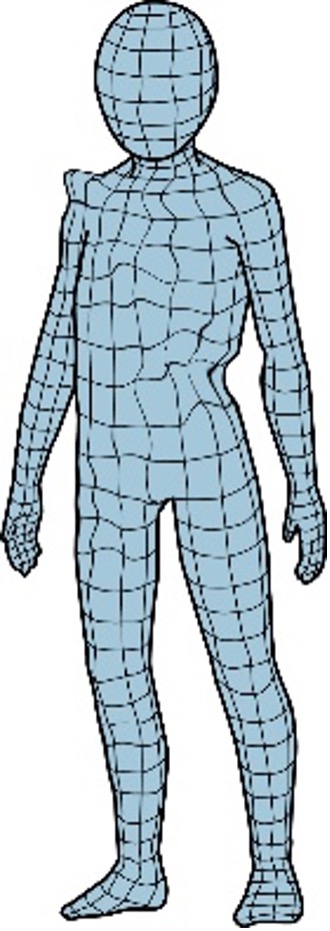
特に外傷の場合は、負荷がかからない安静状態で、循環が良い状態を保つことが、回復を促進するために重要です。
しばしば、安静を保った結果、その箇所が硬くなったり、瘢痕組織ができたりして、動かしづらくなったり、可動域が小さくなったりが起きます。
筋膜リリースと皮膚刺激で、組織の軟らかさを保ち、循環を良くすることは、外傷が起きた組織の回復に、大いに役立つでしょう。
参考文献
- Melzack R, Pain mechanisms: A new theory, Science, 1965 (ゲートコントロール理論)
- Sluka KA, Pain and movement: Integrating science and therapy, J Pain, 2020
- Schleip R, Fascial plasticity and mechanotransduction, J Bodyw Mov Ther, 2012
- Rodríguez-Huguet M, Negative-pressure MFR improves pain and QOL, Clin Rehabil, 2022
- Craig AD, Interoception and pain perception, Nat Rev Neurosci, 2002
よくある質問(FAQ)
Q1. 痛みが取れたらストレッチしていい?
A1.→ 軽い可動ならOKですが、痛みが完全に消えてから48時間は慎重に。
Q2. リリースはどのくらいの圧がいい?
A2. → 「気持ちいい」と感じるレベルが最適。強い刺激は炎症を再発させます。
Q3. ペットへのケアはどうすれば?
A3.→ 犬猫の場合は指先で優しく皮膚を動かすか、陰圧器具で軽く吸引。
Q4. 痛み止めは使ってもいい?
A4. → 急性期はOK。ただし薬に頼りすぎず、循環改善を同時に。
Q5. 筋膜が硬くなるのはなぜ?
A5. → 炎症後にコラーゲンが過剰生成されるため。早期の血流改善が重要。

















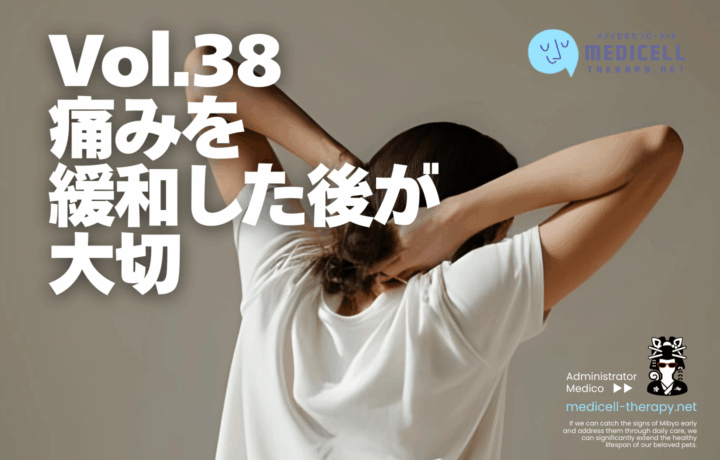









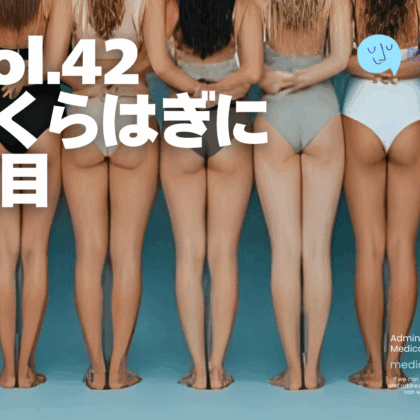





コメント