はじめに:長寿なのに、不健康な国
世界最長寿国・日本。
にもかかわらず、健康寿命との差が世界でも大きい。
体は生きていても、痛み・不調・倦怠・不安・ストレスに悩む人が急増しています。
メンタル疾患の増加、子どもの不登校や発達不調、社会の閉塞感。
これらは「心の問題」とされがちですが、実は身体構造の変化も深く関わっています。
現代日本人の体には、かつてなかった“異変”が起きています。
それが、「身体の硬さ」です。
1. 歴史が語る ― 江戸時代の人は“柔らかかった”
江戸時代の浮世絵を見てみると、描かれた人々の姿勢や動作にはしなやかさが感じられます。
背筋は自然に伸び、肩は開き、腰にはしなやかな張りがある。
現代人が真似しても、この“自然な姿勢”は意外に難しい。
身体運動学の研究によれば、
江戸の庶民は1日に平均7〜10kmを歩き、農作業や物運び、立ち仕事などを通して常に体を使っていました。
それでいて、腰痛や肩こりという概念がほとんど存在しなかった。
一方で現代は、平均歩数はわずか4,000歩前後。
多くの人が座りっぱなしの時間を8時間以上過ごしています。
体を使う頻度が減るとどうなるか?
筋肉が硬くなり、血流が悪くなり、筋膜が癒着する。
その結果、神経も精神もこわばる。
体の“柔らかさ”は、単にストレッチの問題ではなく、
人間の生き方そのものの変化を映しているのです。
2. 「身体の硬さ」がもたらす心の硬さ
心理学者アントニオ・ダマシオ博士は言いました。
「私たちはまず感じ、そして考える。」
体が感じる情報(内臓感覚・筋感覚・皮膚刺激など)は、
すべて脳の情動中枢に送られ、心の状態を形づくります。
つまり――
体が硬くなる=脳への刺激が減る=感情が鈍る。
筋膜が硬縮し、動きが減ると、感覚の入力が減少し、
セロトニン・オキシトシンといった“幸福ホルモン”の分泌も減ります。
これが、現代人の「なんとなく不安」「気持ちが沈む」の一因です。
3. 科学的に見る「柔らかい体はストレスに強い」
柔軟性が高い人ほど、副交感神経が優位になりやすいというデータがあります。
(出典:日本体力医学会誌 2018年)
副交感神経は「リラックス・修復」を司る神経。
体がしなやかに動く人は、ストレス下でも呼吸が深く、心拍が安定している。
反対に、体が硬い人は、
筋肉が常に緊張 → 交感神経が優位 → 心拍上昇・血管収縮・睡眠質低下。
つまり、柔軟性=ストレス耐性のバロメーター。
この観点から見ると、現代人のストレス社会は、
「心が病む前に、体が硬くなっていた」と言えるかもしれません。
最新の研究では、筋膜の柔軟性が循環機能と直結していることが分かっています。筋膜が硬化すると血流・リンパの流れが滞り、酸素や栄養素が細胞に届きにくくなり、老廃物の排出も妨げられます。これが肩こりや腰痛、冷え、むくみ、さらには免疫力の低下につながります。
4. 筋膜の硬化がすべてをつなぐキーワード
筋膜は全身を包む“情報ネットワーク”。
筋肉、神経、血管、内臓までもこの薄い膜でつながっています。
最近の研究では、筋膜の硬化が以下の問題と関連することがわかっています。
- 慢性疲労症候群:筋膜内の循環低下
- 抑うつ傾向:筋膜の硬化による神経伝達阻害
- 免疫低下:リンパ流の停滞
- 姿勢異常:筋膜バランスの崩壊
つまり、筋膜の硬さは「身体」「脳」「心」のすべてを貫く根幹。
“体が硬い=筋膜が緊張している=心が張り詰めている”という構図です。
5. 誤解と神話の整理
❌ 神話①:「硬いけど、動けるから問題ない」
→ 実際には、可動域の減少よりも“筋膜の弾性低下”が深刻。
弾力を失った筋膜は、神経伝達の遅れを引き起こします。
❌ 神話②:「運動不足は筋力低下だけの問題」
→ 筋膜や関節の滑走が減ると、血流・リンパ・ホルモンまで滞る。
体だけでなく、脳と心のパフォーマンスも低下。
❌ 神話③:「ストレッチで柔らかくなる」
→ 筋膜の癒着はストレッチでは届きにくい。
表層から皮膚・筋膜間の**“滑走”を取り戻す刺激**が必要。
💡 神話④:「年齢のせいだから仕方ない」
→ 年齢ではなく、循環と刺激の減少が原因。
皮膚刺激を与えれば、70代でも筋膜は再生します。
6. 科学的根拠:筋膜リリースと柔軟性の再獲得
① 筋膜の硬化は“水分喪失”から始まる
筋膜の主成分ヒアルロン酸が脱水すると、摩擦が増え、滑走が低下。
軽い陰圧刺激で間質液の循環が戻ると、再び潤滑が改善されます。
② 神経伝達と筋膜の連動
筋膜内には自由神経終末が密集。
ここへの刺激が脳の島皮質や前頭葉に届き、情動安定効果をもたらす(Harvard Med, 2019)。
③ 柔軟性トレーニングと自律神経
柔軟性の高い人は、心拍変動(HRV)の値が高く、
副交感神経が優位でストレス回復力が高い(日本自律神経学会, 2021)。
④ タッチ刺激とオキシトシン分泌
軽い皮膚刺激で“安心ホルモン”オキシトシンが分泌され、
不安抑制・免疫強化・筋緊張緩和が起きる(Uvnäs-Moberg, 2015)。
7. 社会的背景と現代病 ― “座りすぎ”が奪った柔軟性
現代日本人の平均座位時間は1日7時間以上(OECD調査)。
デスクワーク・スマホ・車社会で、体を動かす機会は激減。
さらに問題なのは、“動かないストレス”が脳の可塑性を低下させること。
運動刺激は脳内BDNF(脳由来神経栄養因子)を増やし、
記憶・感情・判断力を高める働きがあります。
つまり、柔らかい体=柔らかい脳。
動かない体=思考も硬直。
この連鎖が、現代のストレス社会とメンタル低下を加速させています。
8. 動物の世界から見えるヒント
動物たちは「動く」ことを生きる基本にしています。
犬も猫も、寝て起きたら必ず伸びをする。
これが、筋膜をゆるめ、循環を整える自然のセルフリリース。
現代人が失ったのは、この“当たり前の儀式”。
身体をゆるめることは、動物的な本能に基づく生命の再起動なのです。
9. 「ゆるみ」と「ゆるめる」の本当の意味
「ゆるむ」とは、単にリラックスではなく、
構造的な均衡が戻ることを指します。
筋肉・筋膜・内臓・神経・血管――
これらがバランスよく伸縮できる状態こそ「ゆるんでいる」。
一方で「ゆるめる」は、意識的にその状態を取り戻す行為。
それには、呼吸、皮膚刺激、軽い動き、温熱、音、香り――
あらゆる感覚刺激を総動員することが大切。
つまり、「ゆるめる」とは、全感覚を使った再調律なのです。
10. まとめ ― “柔らかい身体”が社会を変える
現代日本人の不調の根底には、“硬さ”があります。
体が硬く、心が硬く、社会まで硬くなる。
私たちが健康寿命を延ばすために必要なのは、「鍛える」ことだけではありません。
むしろ 身体を“ゆるめて柔らかさを取り戻す”こと が、これからの時代の健康戦略の中心になるでしょう。
逆に言えば、体をゆるめれば、
心がやわらぎ、人との関係性もやさしくなる。
硬直した筋膜や滞った循環では、本来の能力を発揮できません。
逆に、柔らかさを持つ身体はエネルギーの巡りが良く、心の安定にもつながります。
江戸時代の庶民の身体が今よりも柔らかく、生活習慣病が少なかった背景を思えば、私たち現代人が抱える不調の多くは「硬さ」が原因であることに気づけるはずです。
ここで大切なのは、「自分の身体は硬くなりやすい」という前提を理解すること。そのうえで、毎日の小さな習慣に「ゆるめる」時間を組み込むことです。
問題は、「気づかないまま硬さが進行する」ということ。だからこそ、気づいた今この瞬間から行動を始めることが、未来の自分を救う一歩になるのです。
柔らかい身体は、柔らかい社会をつくる。
それが、この国の「根底にある憂い」を解く鍵です。
おわりに
みなさんよくご存じですが、日本人の健康の問題は深刻ですね。
平均寿命は世界一ですが、病気や障害を持って生活している人たちがたくさん。精神的な問題を持つ人も増えています。正確に言うと、増える一方。

子どもの心の健康も、深刻さを増していますね。
こうした状況の原因や背景には、色々な事があります。
これからお伝えしたいのは、現代日本人の身体に起きている、意外に気づかないひとつの現象です。
現代から時代を遡って明治時代、さらに遡って江戸時代。
その時代ごとに遺されている写真や肖像画や、江戸時代では浮世絵などを観てみましょう。
「昔の人の方が、身体に軟らかさ(柔らかさ)を感じる。」
このコラムでも、トップアスリートの筋肉は、驚くほど軟らかいことをお伝えしました。まるでマシュマロや赤ちゃんや身体みたいに。

ハイパフォーマンスの必要条件が、この格段に軟らかい身体。
そして、身体の専門家が指摘するところによると、特に江戸時代では、庶民に至るまで軟らかい身体をしていたと。
確かに、時代が下るにつれて、それ以前には無かった疾病が増えてきていたり。
運動能力に関しても、江戸時代の飛脚に象徴されるように、驚異的な距離を日常的に移動していたり。

こうした時代の経過に伴う健康状態や能力の悪化や衰えの原因が、時代と共に身体が硬くなっていったことにあるとは、身体や運動の革新的な研究者などが指摘するところです。
私たち個人が生まれてからのプロセスを考えてみても、当然ながら赤ちゃんの時はとても身体は軟らかく、長ずるにつれて、硬くなっていきます。
運動能力も、筋力や有酸素能力などは別として、純然たる身体の動きに関しては、小学校高学年や中学生期では、とても良い動きをしますが、20代後半を過ぎると、動きの質が低下していき、年齢と共に衰えて高齢期を迎えます。
健康状態については、言うまでもないでしょう。
こうした変遷は、明らかに、身体の軟らかさ・硬さの変化に同調したと考えられる訳です。

身体が硬くなるプロセスは、本人が気づきにくく、慢性的に進行します。
歳と共に身体のコリを訴える人たちが急増しますね。痛みを訴えるケースも増える。そうした時に、「体が硬くなった。」と実感したり。時々、前屈をやってみて感じるとか。
しかし、身体の軟らか・硬さは、私たちの身体の全組織に起きるものです。
身体組織の軟らかさ・硬さに直結した概念が「身体のゆるみ」です。ところがこの「ゆるむ。」、そして「ゆるめる。」について、まちがった理解や、浅い捉え方がもっぱらになってしまっています。
実は、人間の健康や能力は、身体のゆるみと切っても切れない関係にあるのです。それは動物も同じです。
参考文献
- Schleip R. et al., Fascia as a sensory organ, J Bodyw Mov Ther, 2012
- Uvnäs-Moberg K., The oxytocin factor, HarperCollins, 2015
- [日本体力医学会誌, 2018, 柔軟性と自律神経活動の関係]
- Harvard Medical School, 2019, The body-brain connection in emotional regulation
- OECD Sitting Time Data, 2022
よくある質問(FAQ)
Q1. 硬さって遺伝ですか?
A1. → いいえ。生活習慣とストレスの影響が9割です。筋膜は再生可能です。
Q2. どんな刺激が効果的?
A2. → 軽い皮膚吸引・温熱・深呼吸・ストレッチを組み合わせると効果的。
Q3. 運動不足でもリリースすれば改善する?
A3. → します。筋膜の滑走性を回復するだけでも血流が改善し、柔軟性が戻ります。
Q4. ペットにも通用する?
A4. → 通用します。犬や猫の筋膜構造は人とほぼ同じ。穏やかなタッチが最適です。


















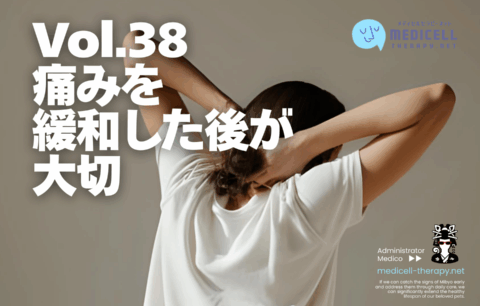





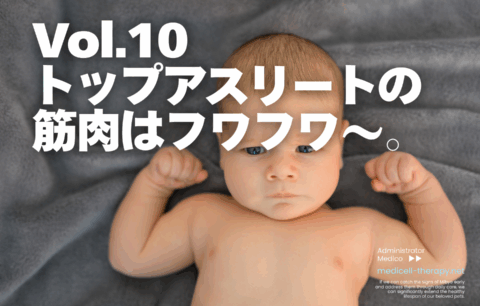











コメント