はじめに:冬の冷えは“ただの体質”ではない
冬になると「手足が冷たい」「布団に入っても温まらない」という悩みを持つ人は多いでしょう。
しかし、よく耳にする「冷え性は女性だけの問題」「厚着すれば解決する」といった考え方は誤解です。実際には、体温調節機能・血液循環・自律神経・生活習慣が深く関わり、放置すると免疫低下・ホルモンバランスの乱れ・慢性疲労につながるケースもあります。
「なんだか体がだるい…」
「手足が冷えて眠れない…」
そんな悩みを抱えているあなた。もしかしたら、それは「血流不足」が原因かもしれません。
私たちの体は、常に36.5度前後の体温を保つことで、正常な機能を維持しています。そして、その体温を維持するために、血液が重要な役割を果たしているのです。
本記事では、最新の研究や日本の実態データをもとに「冷え性の科学的理解と改善方法」を徹底的に解説します。
1. 体温調節の仕組みと血流の役割
人間の体温はおよそ36.5℃前後に保たれることで、酵素反応や代謝が最適に働きます。この「恒常性」を司るのが脳の視床下部です。視床下部は、外気温の変化を感知し、必要に応じて以下の3つの方法で熱を生み出します。
代謝による熱産生(基礎代謝熱)
食事で得た栄養をエネルギーに変える際に発生する熱
仕組み
食べ物から得た栄養(糖質・脂質・タンパク質)をエネルギーに変換する過程で、ATPという「細胞のエネルギー通貨」を作ります。このときに副産物として「熱」が発生します。特に肝臓、脳、心臓、腎臓といった臓器は休んでいるときでもエネルギーを使うため、常に体温維持に大きく貢献しています。
具体例
食後に体がポカポカする「食事誘発性熱産生(DIT)」もこの仕組み。タンパク質は特に熱を生みやすく、摂取エネルギーの約30%が熱に変換されるといわれています。
ポイント
基礎代謝は安静時でも消費されるエネルギーで、体温の6割以上を担っています。加齢や筋肉量低下で代謝熱は減りやすいので、筋力維持が体温維持にも直結します。
ふるえによる熱産生(シバリング)
筋肉を細かく収縮させることで発生する熱
仕組み
寒さを感じると視床下部が自律神経を介して筋肉に命令を出し、「シバリング(ふるえ)」を起こします。これは筋肉を無意識に細かく収縮させることでATPを大量に使い、その副産物として熱を発生させる反応です。
特徴
短時間で大量の熱を生み出す「緊急加温システム」として働きますが、エネルギー消費が大きく、長時間続けるのは不可能です。
具体例
冬に寒さでガタガタ震えるのがこれ。
逆に激しい寒さの中で震えが止まる場合は、低体温症が進んで体が熱産生を諦めている危険サイン。
褐色脂肪組織による熱産生(非ふるえ熱産生)
褐色脂肪組織による熱産生:脂肪を燃焼させることで発生する熱
仕組み
通常の白色脂肪はエネルギー貯蔵用ですが、褐色脂肪組織は「燃焼して熱を作る」特殊な脂肪です。ミトコンドリアを多く含み、UCP1(脱共役タンパク質)という仕組みを使って、エネルギーをATPではなく「熱」として放出します。
存在部位
人間では肩甲骨まわり、首、心臓の周囲、腎臓の周囲などに少量存在。
乳児では多いですが、加齢とともに減少します。
役割
寒冷環境に適応するために働き、特に「長期的に冷えにさらされたとき」に活性化します。近年は、褐色脂肪が多い人ほど肥満になりにくいこともわかっており、肥満治療や代謝改善の研究対象にもなっています。
これらの仕組みによって生み出された熱は、血液によって全身に運ばれます。
- 代謝熱=安定的・ベースの体温維持
- ふるえ熱=短期的・非常時の発熱手段
- 褐色脂肪熱=寒冷適応や代謝コントロールのカギ
👉 視床下部は気温や体温を常にモニターして、これら3つを状況に応じて切り替える「オーケストラの指揮者」のような存在です。
2. 科学的根拠と研究データ
- 体温調節研究:視床下部を中心とした体温恒常性は*Journal of Applied Physiology (2018)*で詳細に報告。
- 冷え性の有病率:厚労省「国民健康・栄養調査」(2023)によれば、女性の約50%、男性の30%が冷えを自覚。
- 血流と免疫:血流不足は免疫細胞供給を阻害し、感染症リスクを上昇させる(Nature Reviews Immunology, 2020)。
- 褐色脂肪組織:寒冷刺激により活性化され、肥満予防や代謝改善にも寄与(Cell Metabolism, 2019)。
- 筋膜ケア研究:吸引+リリースによる血流改善効果が日本リハビリテーション学会誌(2021)で報告。
3. 誤解や神話の整理
神話① 冷え性は女性だけのもの
確かに「冷え性=女性」というイメージは根強いですが、実際は男性も少なくありません。
厚生労働省の「国民健康・栄養調査(2023)」によると、**女性の約50%、男性の約30%**が冷え症状を自覚しているというデータがあります。
女性に多い理由は筋肉量が少なく基礎代謝が低いこと、ホルモンバランスが血管収縮に影響することなどが挙げられますが、男性もストレスや運動不足で血流が滞り、冷えを抱えるケースが増えています。
👉 男性が冷えを見過ごすと、生活習慣病リスクが増大。血流悪化は高血圧・動脈硬化・心疾患の温床となり、働き盛り世代の突然死リスクにも直結します。
神話② 厚着をすれば冷えは解決する
「寒ければ着込めばいい」というのも典型的な誤解。
確かに外部からの保温は重要ですが、冷えの根本原因は毛細血管レベルでの血流不足です。
東京医科歯科大学の研究(Journal of Applied Physiology, 2018)では、皮膚血管の収縮が続くと、どれだけ衣服で覆っても末端部は十分に温まらないことが示されています。
つまり「外側の防寒」だけでなく「内側から血液を巡らせる」工夫が必要なのです。
👉 外から温めるだけで根本対策を怠ると、末端の血管が収縮したまま固定化されます。結果として慢性的な冷え性体質になり、年齢を重ねるほど改善が難しくなります。
神話③ 手足が冷たいだけで健康被害はない
「ちょっと冷たいだけだから大丈夫」と軽く見られがちですが、冷えは放置すると深刻な健康問題につながります。
血流不足が続くと、酸素や栄養の供給が滞り、自律神経失調・免疫力低下・ホルモンバランスの乱れを引き起こす可能性があると報告されています(Nature Reviews Immunology, 2020)。
特に女性では不妊や月経不順との関連も指摘されており、冷えを“軽症”として無視するのは危険です。
👉 慢性的な冷えを放置すれば、自律神経失調・うつ症状・不妊・免疫低下による感染症リスクに発展する恐れあり。特に女性では妊娠や出産に悪影響を及ぼす可能性も。
神話④ サプリメントだけで改善できる
ビタミンEや鉄分、漢方薬などは血流や代謝を助ける作用がありますが、サプリメント単独では根本改善は難しいのが現実です。
体温調節の仕組みは「代謝熱産生」「褐色脂肪組織」「筋肉運動」といった複合システムに依存しているため、運動・生活習慣の改善と併用することが必要です。
実際に、日本リハビリテーション医学会誌(2021)の報告でも、生活習慣介入+理学療法の併用群はサプリ単独群より冷え性改善効果が有意に高いと示されています。
👉 根本原因にアプローチしないまま依存すると、効果が実感できず経済的な無駄になるだけでなく、改善が遅れることで冷え性が固定化。
さらに「効かない=私は体質だから仕方ない」と諦める悪循環に。
神話⑤ 若い人は冷え性とは無縁
「冷え性は年齢とともに出てくるもの」と考えるのも誤りです。
日本産婦人科医会の調査では、20〜30代女性の約6割が冷え症状を経験していると報告されています。
若い人でも、デスクワークによる長時間の同じ姿勢、運動不足、過度なダイエットなどが血流を妨げ、冷えを招きます。
さらにスマホ・PCの長時間使用による自律神経の乱れも、若年層の冷え性の一因と考えられています。
👉 若年層の冷えを軽視すると、将来的な不妊・月経トラブル・代謝不良による肥満や生活習慣病へとつながります。若いうちに血流改善を習慣化できるかどうかが、30代以降の健康寿命を左右します。
4. 血流改善がもたらす効果
冷え性の改善
血流促進により末端の温度が上がり、日常的な冷えが緩和。
自律神経の安定
副交感神経優位になり、睡眠の質やストレス耐性が向上。
免疫力の向上
血流によって白血球が全身を巡り、感染防御機能が強化。
筋膜リリースの科学的有用性
吸引による筋膜リリースで血管が拡張、循環が改善。臨床研究では代謝活性化・むくみ改善・自律神経調整の効果も報告されています。
冬は血流が悪化しやすい!?
寒い季節は、気温の影響で血管が収縮し、血流が悪化しやすくなります。
血流が悪化すると、体熱が全身に運ばれにくくなり、冷えや体調不良を引き起こしやすくなります。
私たちの体の組織や細胞は、血液によって酸素や栄養を供給され、正常な状態を保っています。血流が悪化すると、これらの供給が滞り、様々な不調を引き起こす可能性があります。
まとめ:あなたの「冷え」は、変えられる
冷えや血流の不調は、決して「体質だから仕方ない」と諦めるものではありません。
むしろ、ちょっとした意識と行動の積み重ねで確実に変えていける“改善できるサイン”です。
- 今日からできることは、小さな一歩でいいのです。
→ 寒い日には「湯船に10分」でもOK。
→ 机に座ったまま「肩を回す」でもOK。
→ 夜寝る前に「手足をマッサージ」でもOK。
こうした行動が、血流を少しずつ改善し、やがて「冷えに悩まされない自分」をつくっていきます。
筋膜リリースのように、科学的に裏付けられたケアを取り入れるのも強力なサポートになります。あなたの身体がぽかぽかと温まる感覚は、その瞬間だけでなく、免疫・代謝・心の安定にまでつながる大切な“未来への投資”です。
👉 冷えに悩む自分を「当たり前」とせず、血流を味方につけて健康をデザインする生き方を選びましょう。
👉 その積み重ねが、あなた自身の快適さだけでなく、大切な人と過ごす時間の質をも変えていきます。
- 適度な運動:ウォーキングやストレッチなど、軽い運動で血流を促進しましょう。
- 体を温める:温かい飲み物や食事を摂り、体を内側から温めましょう。入浴もおすすめです。
- 体を締め付けない服装:体を締め付ける服装は、血流を悪化させる可能性があります。
- ストレスを溜めない:ストレスは自律神経を乱し、血流を悪化させます。
- メディセル療法:メディセル療法は、全身の血流を改善する効果が期待できます。
「冷え性だから仕方ない」から、「血流美人として冬を楽しむ自分」へ。
さあ、今日から一緒に歩き出しましょう。
おわりに
寒い季節。気温の影響で、体調を崩す方が多くなります。
人間は体温が36.5度前後に保たれていて、体の機能が正常に働きます。
外気温に影響されて、体温が36.5度前後より高くまたは低くならないように、脳の視床下部が体温調節を行っています。
体温は、以下の三つの方法で生み出されます。
①代謝による熱産生
②ふるえによる熱産生
③褐色脂肪組織による熱産生
これらの仕組みによって、体温が生み出されて、その熱が体中に運ばれます。
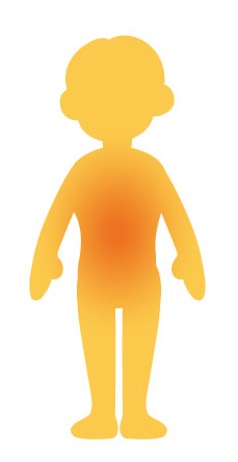
体のどこかがポカポカしている場合は、そこに熱(正確には体熱)が運ばれてきているのですね。逆に冷えているところには、体熱が十分供給されていないということ。
体熱が十分供給されていないところの組織は、本来の機能を充分に行えなくなっています。つまり、健康な状態から外れかけている可能性が。
体熱を運ぶ役割を担っているのは、ズバリ血液ですね。
産出された熱が、液体である血液に保存されます。
何故血液が保存場所になるかというと、液体だから。液体は熱伝導率が低い。どういうことかというと、液体は気体や個体に比べて、熱を逃がしにくい。ですから血液に保存された熱は、失われにくい状態で、身体各部に運ばれます。
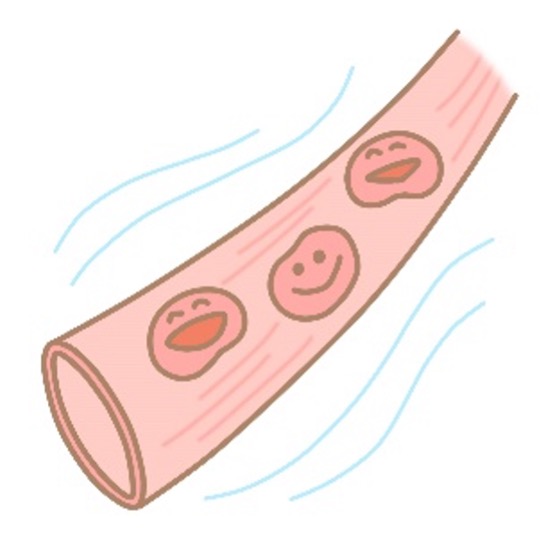
逆に、体のどこかに例えば細菌などが侵入した場合など、その部分に免疫細胞つまり白血球などを送り込まなくてはならないので、血液をより多く送り込みます。または、体全体の血流を早くして、体のあちこちで免疫の働きを促進させます。
その結果、体温が上がり過ぎている状態が起きます。
こうしたメカニズムになっているので、体温は体の状態を知るバロメータとして、必ずチェックされるのですね。

血液が熱をキープしている。
特に寒い季節、体が冷えることが多くなります。ということは、その部分または体全体の血液供給が不十分になっているということに他ならないわけですね。
人間を含め動物の体の組織は、血液によって色々な大切な成分を供給されなければなりません。
体のすべての組織と、それらを構成する細胞は、血液によって正常な状態を保つことができるのです。血流は、私たちが感じている何倍も、健康のために重要な役割を果たしています。

私たちみんな、もっともっと血液循環をよくすることを心掛けたいですね。
もちろんメディセル療法は、体全体の血液循環を善くする、とても良い方法です。
あなたも今日から「血流美人」!
血流を改善して、体の芯からポカポカになり、寒い季節も元気に過ごしましょう!
参考文献(リンク付き)
- 厚生労働省「国民健康・栄養調査」(2023)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/r5-houkoku.html - 経済産業省「健康経営に関する調査」(2022)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei.html - Journal of Applied Physiology (2018)
Thermoregulatory control and human adaptation to cold environments
https://journals.physiology.org/journal/jappl - Nature Reviews Immunology (2020)
The immune system and its regulation by blood flow
https://www.nature.com/nri/ - Cell Metabolism (2019)
Brown adipose tissue: function and therapeutic potential
https://www.cell.com/cell-metabolism - 日本リハビリテーション医学会誌(2021)
吸引刺激による筋膜リリースと血流改善効果
https://www.jarm.or.jp/
よくある質問(FAQ)
Q1. 冷え性は病気ですか?
A. 病名ではありませんが、背景に血管や自律神経の問題がある場合もあります。
Q2. なぜ女性に多いのですか?
A. 筋肉量が少なく代謝が低い、ホルモンバランスの影響で血管が収縮しやすいためです。
Q3. 若い人も冷え性になりますか?
A. はい。特に20〜30代女性の6割が経験しています。
Q4. 褐色脂肪細胞はどうすれば活性化しますか?
A. 冷水シャワー、有酸素運動、首回りストレッチで効果が期待されます。
Q5. サプリや漢方は効果がありますか?
A. 補助的には有効ですが、根本的には血流改善が不可欠です。
A. 血管拡張・血流促進・自律神経調整が臨床研究で示されています。


































コメント