ふくらはぎの腓腹筋とヒラメ筋|第二の心臓を守る筋膜ケアと循環改善の秘訣
「夕方になると脚がパンパンにむくむ」「立ち仕事の後はふくらはぎがだるい」…
そんな経験はありませんか?
実はこの不快感の裏には、ふくらはぎの二大筋肉である 腓腹筋(ひふくきん) と ヒラメ筋 の働きが深く関わっています。両者は“下腿三頭筋”として連動し、足首の動きだけでなく、全身の血流循環や姿勢保持にも大きな影響を与える存在です。
本記事では、腓腹筋とヒラメ筋の違いをわかりやすく整理しつつ、筋膜・循環・予防の観点から日常生活に役立つケア方法を紹介します。読むことで「なぜ疲れやすいのか」「どうアプローチすれば改善できるのか」が理解でき、健康で美しい脚づくりに繋がります。
ふくらはぎの健康は「ヒラメ筋」がカギ
腓腹筋とヒラメ筋は両方とも大切ですが、日常生活において 長時間の立位・歩行・血液循環 を支えるのはヒラメ筋です。特に「第二の心臓」と呼ばれるほど、静脈の血流を押し上げるポンプ機能に優れています。
つまり、ふくらはぎケアや予防の観点では「ヒラメ筋を意識したケア」が最重要ポイントといえるのです。
腓腹筋とヒラメ筋の構造と機能の違い
腓腹筋の特徴:瞬発力とパワー
- 起始部:大腿骨(内側顆・外側顆)
- 特徴:2関節筋(膝・足関節をまたぐ)
- 筋線維タイプ:速筋(Type II)優位
- 主な役割:ジャンプ・ダッシュなど瞬間的動作
- 見た目:ふくらはぎの外観を形づくる二頭型の筋腹
腓腹筋は、瞬間的な力を発揮するための筋肉。
スポーツ動作や坂道ダッシュで主導的に働きます。
ヒラメ筋の特徴:持久力と循環サポート
- 起始部:脛骨・腓骨
- 特徴:1関節筋(足関節のみ)
- 筋線維タイプ:遅筋(Type I)優位
- 主な役割:立位・歩行・姿勢保持
- 機能:静脈還流(血流のポンプ)
ヒラメ筋は疲労耐性が高く、長時間働き続けられる筋肉です。
立ち仕事や歩行の土台になるだけでなく、むくみ防止や冷え対策にも直結しています。
日常での役割とケア法
日常生活での使われ方
- 腓腹筋 → 階段を駆け上がる、ジャンプ、短距離ダッシュ
- ヒラメ筋 → 立ちっぱなし、長距離歩行、デスクワーク中の姿勢保持
ケア・アプローチ法
- カーフレイズ(立位):膝を伸ばして行えば腓腹筋が刺激される
- カーフレイズ(座位):膝を曲げて行えばヒラメ筋を効果的に刺激
- メディセル筋膜リリース:ヒラメ筋は深層にあるため、表面から届きにくい。筋膜の連動を利用するケアが有効
- ストレッチ:ふくらはぎの柔軟性を高めることで、血流改善にも繋がる
科学的エビデンス
研究では、ヒラメ筋の収縮が下肢の静脈還流を促進し、長時間の立位や座位による血流停滞を防ぐことが示されています。また、筋膜リリースによって筋膜の柔軟性を取り戻すと、腓腹筋とヒラメ筋の連動性が高まり、循環効率も向上すると報告されています。
1. ヒラメ筋は「持久力タイプ」
筋肉には「瞬発力に強い速筋」と「長持ちする遅筋」があります。
研究では、ヒラメ筋の約7〜8割が遅筋で構成されているとわかっています。
そのため、長時間立ち続けたり歩き続けたりしても働き続けられるのです。反対に腓腹筋は速筋が多めで、ジャンプやダッシュなどの一瞬のパワーに強い特徴があります。
2. 膝の角度で働く筋肉が変わる
筋電図(筋肉の活動を調べる方法)の実験では、膝を曲げると腓腹筋の働きが減り、その分ヒラメ筋が活躍することが確認されています。
だから「立ってカーフレイズ=腓腹筋中心」「座ってカーフレイズ=ヒラメ筋中心」と言われるのは、単なる経験則ではなく、科学的にも裏づけがあるのです。
3. ふくらはぎは“第二の心臓”
ふくらはぎの筋肉が収縮すると、ポンプのように血液を心臓に押し戻します。
これを「筋ポンプ作用」といいます。
研究でも、ヒラメ筋の働きが弱いと足の血流が滞り、むくみや冷え、さらには血栓リスクまで高まることが指摘されています。逆に、ちょっとした運動やストレッチで筋ポンプが働くと、血流が一気に改善することも確認されています。
4. 座ったままでもケアできる
最近の研究で注目されているのが「Soleus Push-Up(ソレウス・プッシュアップ)」。
これは座ったままかかとを軽く上下させるだけの運動です。
簡単なのにヒラメ筋を選択的に使えるため、血流やエネルギー代謝をサポートする効果が期待されています。オフィスや自宅でも取り入れやすい、いわば“ながら運動”ですね。
5. 筋膜アプローチのサポート効果
カッピングやメディセルなどの筋膜アプローチでは、関節の動きや柔軟性が一時的に良くなるという研究報告があります。さらに血流が増える傾向も確認されていますが、「深部の血流まで届くか」「長期的に効果が続くか」についてはまだ研究段階です。
つまり、セルフケアや運動と組み合わせるとベスト、というのが現状の見解です。
まとめ
腓腹筋とヒラメ筋は、同じ“ふくらはぎの筋肉”でありながら役割が大きく異なります。腓腹筋は瞬発的な動作を支え、ヒラメ筋は長時間の姿勢保持と血流循環を支える——この違いを理解すると、日常生活で感じる脚の疲労や不調の原因が見えてきます。
特にヒラメ筋は「第二の心臓」と呼ばれるほど、全身の循環に直結する筋肉です。冷え・むくみ・だるさを改善するには、見た目に目立つ腓腹筋だけでなく、深層にあるヒラメ筋をケアすることが不可欠です。
しかし、深層筋へのアプローチは難しく、自己流のストレッチやマッサージでは届きにくい部分もあります。そこで効果的なのが、筋膜のつながりを利用したアプローチやメディセルのような専用ツールによるケアです。筋膜を通じてヒラメ筋へアプローチすることで、血流改善や疲労回復を効率的に促すことができます。
あなたのふくらはぎが「むくみやすい」「冷えやすい」「疲れやすい」と感じるのは、単なる筋力不足ではなく、ヒラメ筋のコンディションが低下しているサインかもしれません。今後の健康維持や予防のために、今日から意識的にケアしてみてはいかがでしょうか。
おわりに
腓腹筋(ひふくきん)とヒラメ筋は、いずれも下腿(ふくらはぎ)に位置し、下腿三頭筋を構成しています。両者は共に足関節の底屈(つま先を下げる動き)に関与しますが、起始部・解剖構造・機能・使われる場面・筋線維のタイプなどにおいて明確な違いがあります。

その特徴は以下の通りです。
| 特徴項目 | 腓腹筋 | ヒラメ筋 |
| 起始部 | 大腿骨(大腿骨内側・外側顆) | 脛骨・腓骨(腓骨頭と脛骨後面) |
| 停止部 | アキレス腱を介して踵骨に付着 | アキレス腱を介して踵骨に付着 |
| 関節またぎ数 | 2関節筋(膝関節と足関節) | 1関節筋(足関節のみ) |
| 主な作用 | 足関節の底屈+膝関節の屈曲 | 足関節の底屈 |
| 筋線維タイプ | 速筋(Type II)優位 | 遅筋(Type I)優位 |
| 動作特性 | 瞬発的・パワー系の動作に関与 | 持久的・姿勢保持に関与 |
| 日常生活での役割 | ジャンプ、ダッシュなど瞬間的動作 | 立位・歩行・姿勢保持などの持続的動作 |
| 筋腹の形状 | 目立つ二頭型の筋腹 | 幅広く扁平で深層に位置 |
| 位置関係 | 表層 | 深層(腓腹筋の下層) |
腓腹筋は、表層にあるため、ふくらはぎの外観上の形状を形作ります。
速筋線維が多く、爆発的な収縮力を発揮します。膝関節をまたぐため、膝が伸展している時に最も強く働き、ジャンプ,坂道ダッシュ,つま先立ち動作などで主動筋となります。

ヒラメ筋は、腓腹筋の深層にある扁平な筋肉で、遅筋線維が多く、疲労耐性が高いのが特徴。
疲れにくい筋肉です。
膝関節をまたがないため、膝の角度に関係なく働いて、長時間の立位保持や歩行,安定性維持に重要な働きをします。“
第二の心臓”とも呼ばれるポンプ機能に関与し、静脈還流を助けるという大きな機能を持っています。

腓腹筋は、膝を伸ばした状態でのカーフレイズ(立位など)で、ヒラメ筋は、膝を曲げた状態でのカーフレイズ(座位など)で刺激されます。
腓腹筋が衰弱すると、ジャンプや走力が低下。
ヒラメ筋が衰弱すると、長時間の立位が困難になったり、バランス機能の不良が起きます。
両者はともにアキレス腱に連結し、共同して足関節底屈を行いますが、運動条件や負荷によって主導する筋が異なります。短距離走やジャンプでは腓腹筋が主動筋となり、長距離歩行や姿勢保持では、ヒラメ筋が主動筋となります。
こうしてみると、日常生活においては、ヒラメ筋が果たす役割が大きいですね。立ったり座ったり、歩いたり、姿勢を保ったり、そして第二の心臓として、血液循環に関わったり。

ヒラメ筋は深層筋で、腓腹筋の下に在りますので、表面からのアプローチでヒラメ筋を緩解するのが難しかったりします。そこで、筋膜の連動性を活かしたアプローチが、コンディショニングの一助になるとされています。










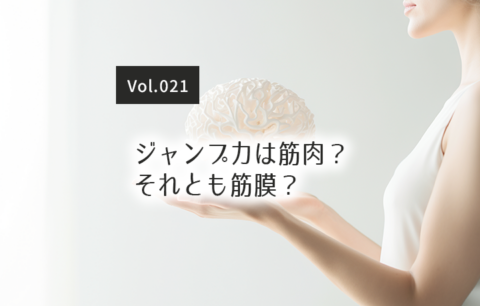


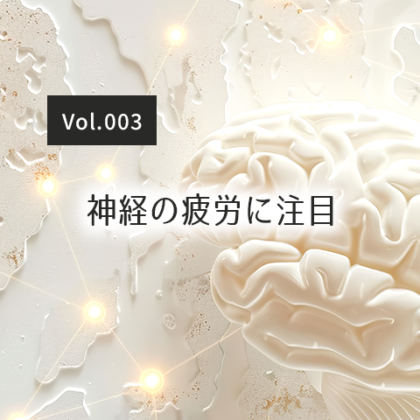

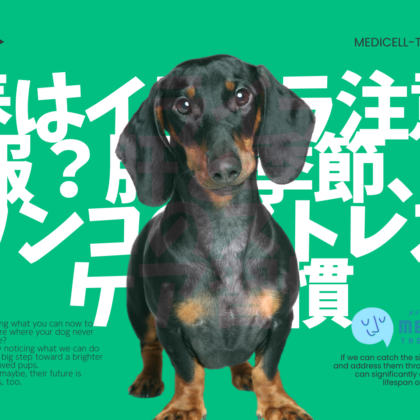



コメント