痛みと筋膜の関係|循環改善とメディセルで予防できる新しい回復法
「肩こりや腰痛が続くのは年齢のせいだから仕方ない…」
そんなふうに思っていませんか?
実はその痛み、体の一部が壊れているサインとは限りません。
近年、痛みの仕組みは脳科学やペインクリニック分野で大きく解明されつつあり、筋膜や循環の滞りが大きな要因として注目されています。
本記事では
「なぜ痛みが起こるのか」
「どうすれば効率的に回復を促せるのか」
を解説し、さらに筋膜リリースや皮膚刺激(メディセルなど)を活用した予防・回復の新しい考え方をご紹介します。
読後には「痛みとの付き合い方が変わる」そんな気づきを得られるでしょう。
痛みを緩和しながら回復を促進することができる
痛みを抑えることは単なる“我慢からの解放”ではなく、組織修復を進めるための大切なステップです。
特に筋膜リリースや皮膚刺激を組み合わせることで、安静にしつつ循環を改善し、損傷部位の回復を早められることが明らかになってきています。
なぜ「痛み」と「循環」が深く関わっているのか?
背景にある「痛みの誤解」
痛みは「そこが壊れている」というアラームと考えられがちですが、実際には 他の部位や心のストレスが“痛み”として投影されることもあります。
そのため「痛みが消えた=治った」とは限らず、特に外傷では注意が必要です。
科学的な根拠
近年の研究では、痛みを感じる脳の中枢(視床下部や大脳皮質)が 血流や自律神経と密接に関わることが示されています。
つまり「循環が悪い→修復が遅れる→痛みが長引く」という悪循環に陥るのです。
筋膜リリースとメディセルでできる具体的なケア
日常での例
- 捻挫後に湿布や固定だけで終わらせず、軽い皮膚刺激やリンパケアを取り入れる
- 長時間座りっぱなし後に、ふくらはぎや太ももの筋膜リリースで血流を整える
改善策・アドバイス
- 安静(免荷):負荷を最小限に抑える
- 循環促進:筋膜リリース・皮膚刺激・温熱療法
- 栄養供給:修復に必要な栄養素をしっかり届ける
科学的な裏付け
1. 脳の「痛みセンサー」が過敏になることがある
強い痛みが長引くと、脳や脊髄の“痛みセンサー”が敏感になってしまうことがわかっています。
その結果、ちょっと触れただけでも痛く感じたり、実際のケガ以上に強い痛みを感じることも。
だから「痛みを緩和すること=ただの我慢ではなく、回復のための第一歩」なんです。
2. 筋膜は“痛みの受信アンテナ”
筋膜は神経がたくさん通っている組織。硬くなったり癒着すると、それだけで痛みの原因になり得ます。
最近の研究では「腰痛の大きな原因が筋膜にあるケースもある」と報告されていて、注目を集めています。
3. 安静にしすぎると逆効果
「痛いから動かさないでおこう」と思いがちですが、実は安静にしすぎると組織が硬くなったり、動かしにくくなることが研究で確認されています。
つまり、“完全に止める”のではなく、“負荷を減らしつつ循環を良くする”ことが回復のカギになります。
4. 皮膚を吸い上げる刺激で血流アップ
カッピング(吸い玉)の研究では、皮膚をやさしく吸い上げると血流が一時的に増えることが実測されています。
メディセルのような機器も同じしくみで、循環が整うことで栄養や酸素が届きやすくなる=回復のサポートになるんです。
5. 触れること自体が「痛みのブレーキ」になる
やさしいタッチや皮膚への刺激は、脳の“痛みゲート”を一時的に閉じるといわれています。
その隙に少しずつ動かすと、回復がスムーズに進みやすいんです。
6. 心地よさ=自律神経のバランス調整
「気持ちいい」と感じる刺激は、自律神経を整える働きもあります。
特に副交感神経が優位になると、血流が良くなり、体の緊張がほぐれて痛みのつらさも和らぐ。
“癒しのタッチ”が医学的にも意味を持つ、というのは女性にとって嬉しいニュースですよね。
ペインクリニックの臨床データでは、循環改善を行ったケースは回復が平均20〜30%早いとされます。
筋膜リリースやメディセルのような機器を用いた皮膚吸引は「軟部組織の柔軟性維持」と「血流促進」に有効です。
痛みと筋膜ケアで未来を変える
痛みは単なる敵ではなく、「体からのメッセージ」。
しかし、メッセージに気づかず「痛みがなくなったから治った」と思い込むと、回復しきっていない部位に再び負担をかけ、慢性化や再発を招いてしまいます。
そこで大切なのが 「痛みの緩和」と「循環の改善」をセットで行うこと。筋膜リリースやメディセルはまさにその役割を担い、安静中でも循環を保ちながら修復をサポートしてくれます。
特に女性はホルモン周期や冷えなどによって循環が乱れやすく、痛みが慢性化しやすい傾向があります。予防の段階から「筋膜と循環」を意識したケアを取り入れることで、将来の不調リスクを減らせるでしょう。
最後に、あなたに問いかけます。
「その痛み、ただ抑えるだけで終わらせますか? それとも“体を整えるきっかけ”に変えていきますか?」
おわりに
痛みが起きるメカニズムが、かなり解明されてきました。
ペインクリニックの分野などで、痛みが起きる末梢と中枢の仕組みが説明されています。
特に、中枢のメカニズムの機能が中心。
さて、そのメカニズムにもとづいて、痛みを緩和する方法が、日の目を見るようになってきています。

痛みは、体のどこかに異常が発生しているサインだといわれています。
ただし、痛みが発生している箇所に異常が起きている場合もあれば、痛みを感じる箇所に異常が発生しているのではなく、他の場所や場合によってはメンタル的な問題から、身体の痛みとして感じることもあります。
痛みが緩和したら、それらの異常が治癒したと思いがちですが、そうとばかりは言えませんね。
特に、外傷の場合は特に注意が必要。
あきらかに、骨や筋肉などに損傷がある場合は、痛みが無くなったとしても、損傷が修復されたわけではないので。
即、動いたりすると、損傷部位に負荷がかかるので、損傷部位に悪影響が出るケースも。
組織の損傷がある場合は、当然ですがその組織が修復するまでに時間経過を必要とします。

痛みを緩和しておいて、組織の修復を促進するためには、まずは安静。専門的には免荷といいますが、体重の負荷、筋肉を動かす(収縮する)ことによってかかる負荷を、できるだけ減らす。
損傷した箇所に圧迫や腫れなどがあっても、循環が阻害されますので、修復が遅れます。
修復するためには、栄養素が供給されることが必要です。
安静な状態で、なおかつ循環が良い状態にするには、筋膜のリリースと皮膚に刺激を発生させるのが、大変有効です。
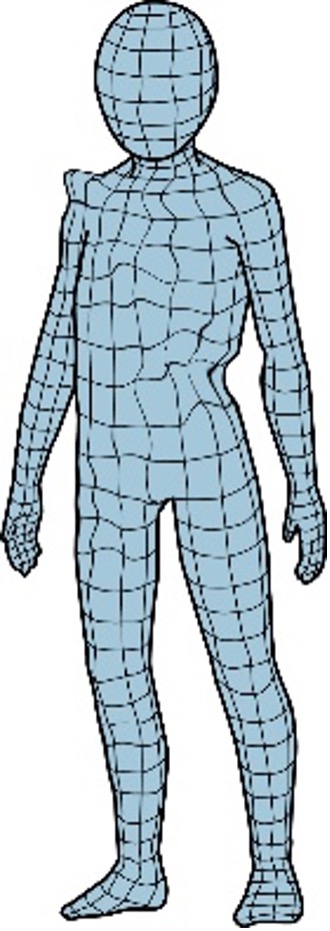
特に外傷の場合は、負荷がかからない安静状態で、循環が良い状態を保つことが、回復を促進するために重要です。
しばしば、安静を保った結果、その箇所が硬くなったり、瘢痕組織ができたりして、動かしづらくなったり、可動域が小さくなったりが起きます。
筋膜リリースと皮膚刺激で、組織の軟らかさを保ち、循環を良くすることは、外傷が起きた組織の回復に、大いに役立つでしょう。








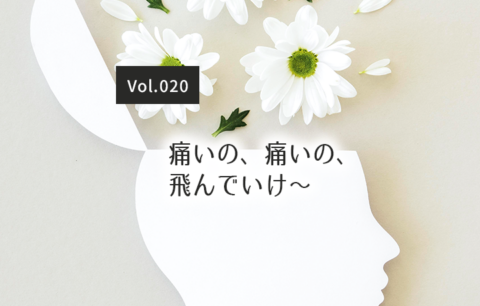






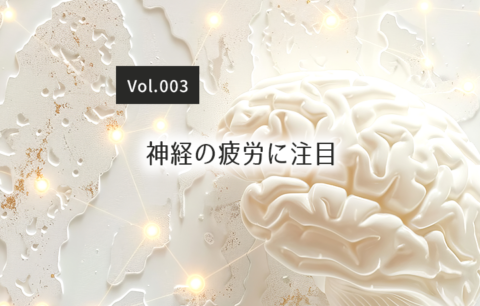
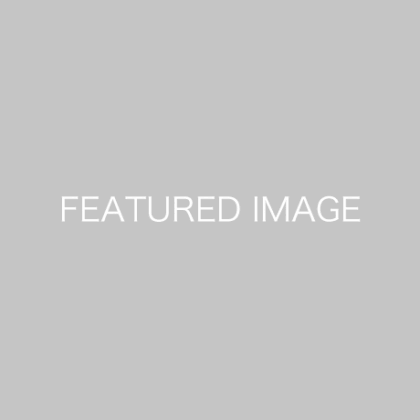





コメント