人間の手の構造がもたらす驚異的な影響
「手は第二の脳」と言われるほど、人間の手は脳と密接な関係にあります。特に、親指と他の4本の指が向かい合う構造は、人間と一部の霊長類だけが持つ特別なものです。この構造こそが、私たちが文字を書いたり、複雑な機械を操作したりできる理由なのです。
手の構造とその進化的な優位性
人間の手は、親指と他の四本の指が向き合うことで、他の動物の手と大きな違いがあります。この「対向性のある手」は、物をつかんだり、操作したりする精密な動きを可能にし、道具を使ったり、文字を書いたりする能力を生み出しました。これが、機械や技術の発展に大きく寄与しています。
手の進化が特に注目されるのは、その多様性にあります。手は、物をつかむ、持つ、握る、触れる、描く、書くなど、様々な動作を精密に行うことができ、その全てに精密な筋肉が関与しています。このように、手は体内で最も複雑な動きをする部位の一つです。
顔と手の複雑な動き
顔と手は、人体の中でも最も複雑で多様な動きをします。手の細かい筋肉が手のあらゆる動きに関わり、同時に顔も表情や細かな動きによって情報を脳に送ります。これらの動きや感覚は、脳と密接に連動しており、手と顔は、脳に強い影響を与える部位です。
手は、触れることで様々な感覚情報を脳に伝え、例えば温度や硬さ、柔らかさ、さらには感情や状態を感じ取ることができます。このため、手の感覚が鈍くなったり、動きが硬くなったりすると、脳に送られる情報が減少し、脳の働きに影響を与える可能性があります。
手と脳の深い関係
手と脳には深い関係があり、手の動きや感覚が脳の働きに影響を与えることが確認されています。特に、手が硬くなると、脳に送られる刺激や情報の量が減少し、脳の働きが低下する可能性があります。これは、パソコンやスマホを長時間使用する現代の生活環境で特に顕著です。
現代の生活では、手の使い方が単調になりがちです。キーボードを打つことが多く、手の細かな動きが減少しています。そのため、手の感覚や動きが硬直してしまうことがあり、これが脳に与える影響は無視できません。
また、子どもたちの手の発達にも影響があります。屋外で遊ぶ機会が減少し、自然の中で多様な物に触れる機会が減ることで、手の感覚が育たず、脳への刺激も不足しがちです。これが、知的発達や情緒的発達にとってマイナスになる可能性があります。
手を使う重要性
手を柔軟に使うことが、脳への刺激となり、脳の健康にとって重要です。長時間同じ動きを繰り返すと、手が硬くなり、脳への情報が減少するため、手の状態を意識的に改善することが大切です。手のストレッチやマッサージ、手作業を増やすことなどで、手を柔軟に保つことが脳の活性化にも繋がります。
手が硬いと脳の働きが低下する!?
現代人の多くは、パソコンやスマートフォンの長時間使用により、手の動きが単調になりがちです。その結果、手が硬くなり、脳への刺激が減少してしまうのです。脳は、多様な刺激を受けることで活性化するため、手の硬直は脳機能の低下に繋がる可能性があります。
握手でわかる!手の状態と脳の関係
握手をすると、人によって手の感触が全く異なることに気づきます。温かさ、硬さ、柔らかさ、そして手の形。これらの違いは、その人の生活習慣や健康状態を反映している可能性があり、脳の状態にも影響を与えているかもしれません。
現代生活と手の変化
- **パソコン作業の増加:**キーボード操作は反復運動であり、手の筋肉を硬くする原因になります。
- **手書きの減少:**鉛筆やペンを使った手書きは、多様な手の動きを促しますが、現代では減少傾向にあります。
- **子供の外遊び減少:**自然の中で様々なものに触れる機会が減り、手の感覚発達に影響が出ています。
手の柔軟性を保つための対策
- 定期的な手のストレッチやマッサージ
- 手を使った趣味(料理、手芸、楽器演奏など)
- 意識的に多様なものに触れる機会を増やす
まとめ
人間の手は、進化の過程で非常に重要な役割を果たしてきました。手の構造が精緻であるからこそ、人間はさまざまな道具を使い、創造的な活動を行えるのです。しかし、現代の生活では手の使い方が単調になり、手が硬くなることが脳への刺激を減少させ、健康や発達に影響を与える可能性があります。手の状態を意識して柔軟に使うことが、脳の活性化にも繋がる大切なポイントです。
手の状態は、私たちの脳機能に大きな影響を与えます。日頃から手の柔軟性を意識し、多様な動きを取り入れることで、脳を活性化し、健康的な生活を送りましょう。
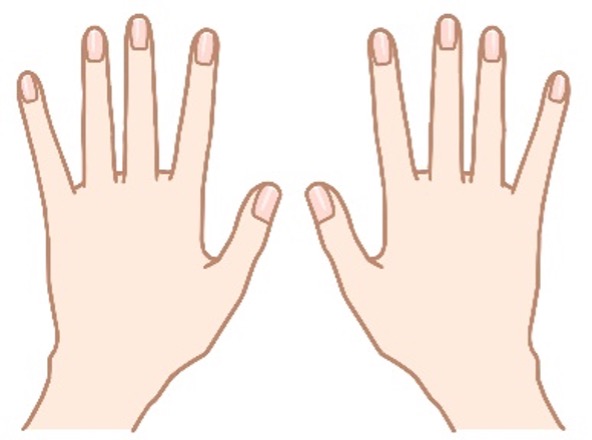
おわりに
人間の手、とても素晴らしいですね。
親指とその他の四本の指が向き合う手の構造をしているのは、お猿さんたちと人間だけですね。この手の構造を持っているから、手の働きが飛躍的に進化したとされています。
文字を書くのも、親指と他の四本の指が向き合って使えるから、可能なのですね。
改めて言うまでもなく、人間が創造した無数の機械などは、人間のこの手の構造だからこそなのだということは、既に定説となっています。
ヒトの手は、実に多様な動きをします。体の中で、顔と手が、最も複雑な動きをします。
それだけに、細かい筋肉が、顔にも手にもありますね。
と同時に、顔と手は、感度が抜群に高いですね。敏感に、色々な刺激や情報を感受しています。
だから、顔と手に関係している脳の領域は、抜群に広いのですね。
ということは、顔はもちろん、手の動きや手が感じとる刺激や情報は、脳に対しての影響が大きいということですね。
これはとても大切なポイントです。

手の状態がどうかによって、脳への影響が変わるのですね。
もし手が硬くなっていたら、脳に送られる刺激や情報の量は減少します。そうなると、脳は入力される刺激や情報によって活性化しますので、脳の働く水準は下がっていきます。
手と脳の深い関係。
色々な人と握手すると、その人ごとに手の感触がちがうことに驚きます。
手の形や大きさはもちろん、温かさや硬さ・軟らかさ。
そして、相手の手の感触によって、自分の中に起きる反応が変わるのに気づきます。
パソコン作業全盛の今、手先指先を使っているように思いがちですが、その使い方が画一的になっています。それが証拠に、長時間キーボードを打つと、手や指は硬くなってしまいます。字を書くにも、ワープロがメインです。かつては鉛筆やペンで文章を書いていましたから、それと比べると、手の動きのパターンが激減です。その他にも、日常生活の中での手作業のバリエーションは、減る一方と言ってよいでしょう。

子どもたちにとっても、屋外や自然の中での遊びが、これまた激減しているということは、様々な物に触れる機会が激減。その結果、脳が受ける刺激や情報が激減。
子どもの知的発達や情緒的発達にとって、マイナス要因であるという指摘もされています。

手が硬くなる。意外に気づいている人は少ないでしょうが、生活の中に潜む、健康や発育発達など、幅広い領域に関係している、大切なポイントなのですね。
筆者:竹内 研(一般社団法人日本メディセル療法協会理事・学術委員長)



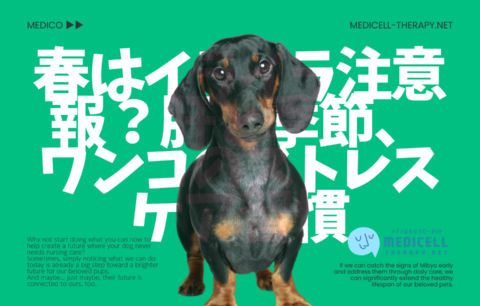








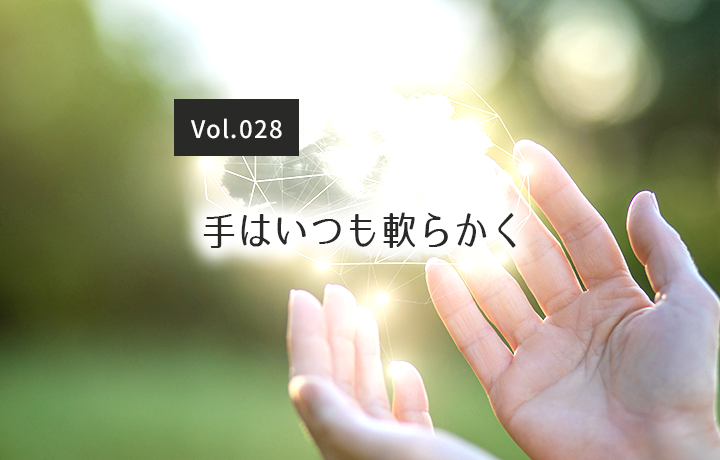

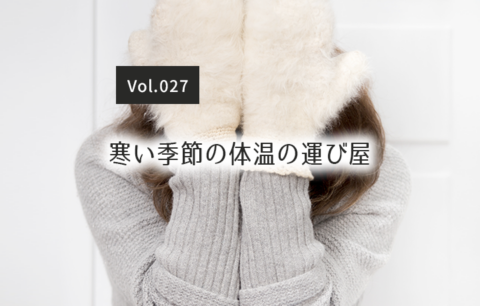

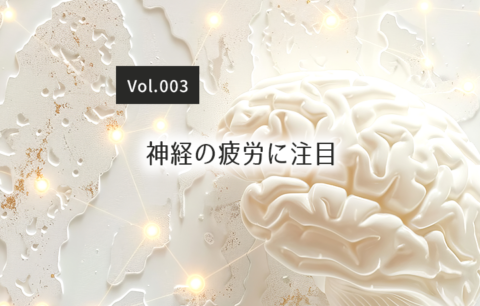
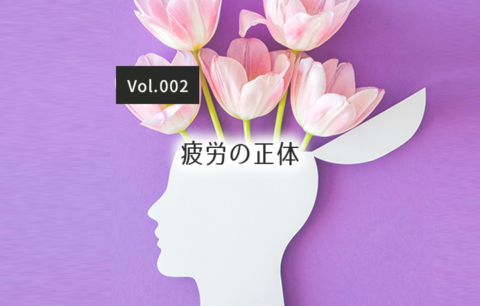

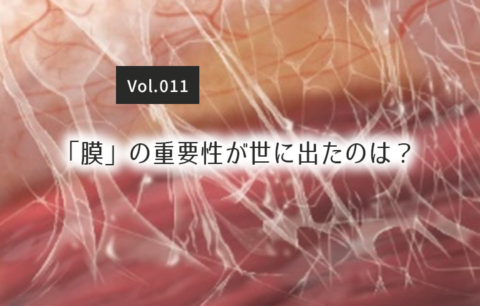
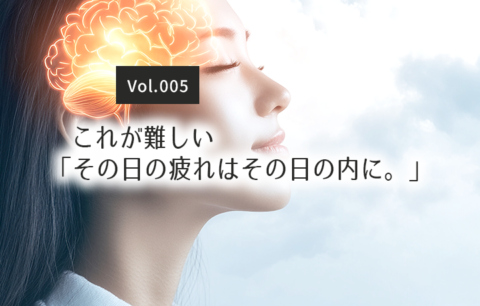

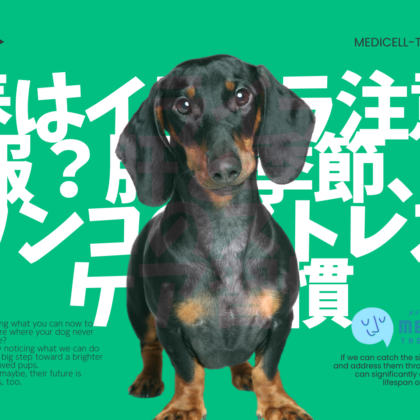
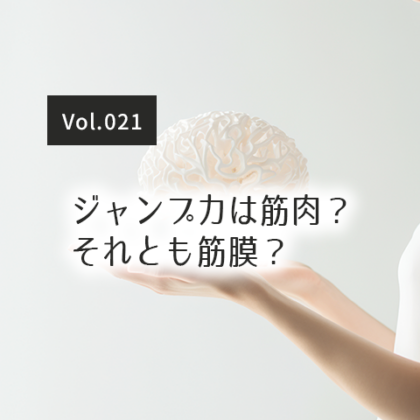



コメント