「もっと自由に動けたら…」
「構えが安定せず、呼吸が乱れやすい…」
「足運びが重く、相手の動きについていけない…」
こうした悩みを抱えている方は多いですが、実は「筋膜」が原因になっていることをご存じでしょうか?
武術や格闘技において、力強さとしなやかさを両立するには、筋肉だけでなく**“巡り”**を意識することが不可欠です。
**この“巡り”を整える鍵となるのが「筋膜」です。
古代中国の伝承医学では、筋膜に似た概念として「経絡(けいらく)」**があり、これが武術や健康法の基礎となってきました。
中でも「易筋経(えききんきょう)」は、達磨大師が伝えたとされる体の鍛え方で、筋膜の巡りを整え、動きの質を高める要素が詰まっています。
本記事では、
✅ なぜ筋膜が“巡り”と関係しているのか?
✅ 伝承医学で説かれる「筋膜と気の流れ」の秘密
✅ 易筋経を活かした「構え・呼吸・足運び」の調整法
を科学的な視点と伝承医学の知恵を組み合わせて解説します。
筋膜と伝承医学がつなぐ“巡り”の感覚
結論として、武術・格闘技において「構え・呼吸・足運び」を整えるには、筋膜の“巡り”を意識することが必要不可欠です。
筋膜は、筋肉・内臓・血管・神経を包み込み、全身をネットワークのようにつなげています。
この筋膜が硬くなり癒着すると、血流が滞り、可動域が狭まり、パワーが分散されてしまいます。
結果として、構えの安定性が失われ、足運びが重くなり、呼吸の質も低下してしまうのです。
伝承医学の知恵である**「易筋経」**は、この筋膜の働きを活性化し、流れをスムーズにするための動作を含んでいます。
「力を込める」よりも「巡らせる」ことで、本来のしなやかで強い動きを取り戻せるのです。
「巡り」とは何か? 伝承医学と科学の共通点
古代中国の伝承医学では、「巡り(めぐり)」という言葉が重要視されてきました。
これは、経絡や気血の流れを最適化することで、身体の機能を高める考え方です。
一方、現代科学においても「血流・リンパ・神経伝達」の最適化が、健康やパフォーマンス向上に大きな影響を与えることが明らかになっています。
この「巡り」の概念を具体的に見ると、以下のような要素が含まれます。
- 血液の流れ(酸素・栄養の供給)
- 適切な血流が、筋肉・内臓の働きを支える。
- 血行が悪いと筋膜が硬くなり、可動域が低下。
- リンパの流れ(老廃物の排出)
- リンパの滞りは、むくみや疲労の蓄積を引き起こす。
- 筋膜の癒着はリンパの流れを妨げ、回復を遅らせる。
- 神経の伝達(筋肉の動きと感覚)
- 筋膜は神経とも密接に関係し、感覚の鋭敏さに影響。
- 筋膜が整うことで、身体の反応速度が向上。
つまり、「筋膜が巡りを整える鍵である」ことは、伝承医学と現代科学の両方において一致しているのです。
なぜ筋膜の“巡り”が重要なのか?
筋膜が動作を支配するメカニズム
現代科学では、筋膜が「第二の骨格」とも言われ、全身の連動性や動きのスムーズさを決定づける要素として注目されています。
筋膜の健康状態が良好であれば、体の各部位がスムーズに連携し、無駄な力みがなくなります。
一方、筋膜が癒着すると、筋肉の柔軟性が低下し、力がうまく伝わらなくなります。
これは、まるで詰まった水道管のような状態。
いくら水(エネルギー)を送り込んでも、スムーズに流れなければ意味がありません。
これと同じことが、構え・呼吸・足運びにも影響を与えます。
筋膜の滞りが、体の一体感を失わせ、スムーズな動きを阻害してしまうのです。
「巡り」とは何か? 伝承医学と科学の共通点
古代中国の伝承医学では、「巡り(めぐり)」という言葉が重要視されてきました。
これは、経絡や気血の流れを最適化することで、身体の機能を高める考え方です。
一方、現代科学においても「血流・リンパ・神経伝達」の最適化が、健康やパフォーマンス向上に大きな影響を与えることが明らかになっています。
この「巡り」の概念を具体的に見ると、以下のような要素が含まれます。
- 血液の流れ(酸素・栄養の供給)
- 適切な血流が、筋肉・内臓の働きを支える。
- 血行が悪いと筋膜が硬くなり、可動域が低下。
- リンパの流れ(老廃物の排出)
- リンパの滞りは、むくみや疲労の蓄積を引き起こす。
- 筋膜の癒着はリンパの流れを妨げ、回復を遅らせる。
- 神経の伝達(筋肉の動きと感覚)
- 筋膜は神経とも密接に関係し、感覚の鋭敏さに影響。
- 筋膜が整うことで、身体の反応速度が向上。
つまり、「筋膜が巡りを整える鍵である」ことは、伝承医学と現代科学の両方において一致しているのです。
「巡り」の概念と筋膜の科学的視点
易筋経が説く「巡らせる動き」と筋膜の関係
易筋経では、「筋肉を鍛えるだけでなく、巡らせることが重要」と説かれています。
これは、現代のスポーツ科学における「ファンクショナルトレーニング」や「筋膜リリース」とも共通する考え方です。
易筋経の動作には、以下のような特徴があります。
- ゆっくりとした波のような動き(筋膜の滑走性を高める)
- 呼吸と連動した動作(自律神経を整え、パフォーマンスを向上させる)
- 全身のつながりを意識する(部分的な筋力ではなく、連動性を高める)
これらは、まさに筋膜の働きを最大限に活かす動きと言えます。
具体的な筋膜ケアと実践方法
易筋経の動きを取り入れる
- 立ち姿勢での「波動動作」(全身をしなやかに使うための準備)
- ゆっくりした深い呼吸とともに体を動かす(呼吸と筋膜の連携を意識)
- 手足を大きく使い、全身を連動させる(局所的な動きではなく、筋膜全体を活性化)
セルフ筋膜リリース
- フォームローラーを使い、筋膜を緩める(足・背中・肩の順番で実施)
- 呼吸を深めながら圧をかける(リラックスした状態で行うと効果UP)
まとめ
「強くなること」と「巡らせること」は、武術や格闘技において切り離せない要素です。
筋膜の健康状態を整えることで、構えが安定し、呼吸が深まり、足運びが軽やかになります。
易筋経は、単なる体力トレーニングではなく、筋膜の巡りを整え、体をスムーズに動かすための知恵です。
現代の筋膜リリースやスポーツ科学と組み合わせることで、新しい武術トレーニングの形が見えてくるでしょう。
あなたの体は、もっとしなやかに動けるはず。
伝承医学と現代科学の融合で、新たな可能性を追求してみませんか?
medicell-therapy.net
おすすめ関連記事





















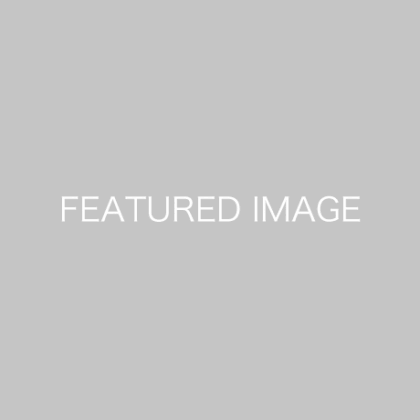





コメント